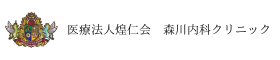②睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群とは何か?
医学的定義と種類(閉塞性・中枢性・混合型)
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり弱まったりする病気です。
医学的には「10秒以上の無呼吸状態が1時間あたり5回以上ある」ことで診断されます。
こうした無呼吸や低呼吸(呼吸が浅く弱くなる状態)が繰り返されると、酸素不足を引き起こし、睡眠の質が著しく低下します。
SASには大きく3つのタイプがあります。
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)
最も一般的なタイプで、全体の約9割を占めます。睡眠中に喉(上気道)が塞がり、空気の流れが遮断されるのが原因です。
肥満や顎の小ささ、舌の大きさなど解剖学的な特徴が関係しており、激しいいびきと「呼吸が止まっては再開する」現象が特徴です。
中枢性睡眠時無呼吸(CSA)
脳が「呼吸せよ」という信号を出せなくなるタイプです。心不全や脳疾患、薬剤の影響などが背景にあります。
発生頻度は少ないものの、重症化するケースもあります。
混合型睡眠時無呼吸(MSA)
OSAとCSAの両方が同時に起きるタイプです。
初期は閉塞性だったものが進行するにつれて中枢性の要素が加わり、混合型に移行する場合もあります。
放置のリスクと影響
この病気が厄介なのは、「眠っている間に静かに進行する」という点です。
無呼吸による酸素不足が繰り返されると、交感神経が過剰に刺激され、血圧が上昇しやすくなります。
その結果、慢性的な高血圧を招き、さらに心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる疾患のリスクを大きく高めます。
また、質の低い睡眠が続くことで、成長ホルモンや免疫機能の分泌にも悪影響が及びます。
そのため、単なる日中の眠気にとどまらず、抑うつ状態・記憶力の低下・仕事や学業のパフォーマンス低下など、
生活のあらゆる面に悪影響が広がります。
さらに注目すべきは、「糖尿病との関連性」です。SAS患者はインスリン抵抗性が高まりやすく、糖尿病をはじめとする生活習慣病との関係も明らかになっています。
なぜ気づかれにくいのか?
睡眠時無呼吸症候群は、自分で気づきにくい病気です。というのも、症状の中心が「睡眠中」に現れるからです。
無呼吸やいびきは本人が覚えていないことが多く、「家族からの指摘」で初めて発覚するケースがほとんど。
単身者や一人暮らしの高齢者では特に見逃されやすい点が問題です。
次回は、「こんな症状があれば要注意」と題し、セルフチェックの方法や初期症状の見分け方を載せていきます。