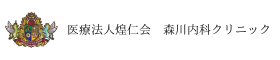エムポックス
エムポックス(旧サル痘)とは?症状・潜伏期間・感染対策まで徹底ガイド
この記事でわかること
このガイドでは、以下のポイントについてやさしく・わかりやすく解説します:
- ✅ エムポックス(旧サル痘)とは?
- ✅ エムポックスの症状と潜伏期
- ✅ 潜伏期間と感染のタイミング
- ✅ まとめ:症状を見逃さないことが予防の第一歩
- ✅ まとめ:誰にでも起こり得る感染だからこそ、冷静に対応を
- ✅ まとめ:現状は“収束”ではなく“継続的な注意”が必要
- ✅ まとめ:予防の基本は「正しい行動と正確な知識」
- ✅ まず確認したい「症状」と「状況」
信頼できる公的情報をもとに、エムポックスへの理解を深め、不安から安心へとつなげることを目指します。
🟠 はじめに:エムポックス(旧サル痘)とは?
◆ 「エムポックス」って聞いたことありますか?
かつて「サル痘」と呼ばれていたこの感染症。
現在では**「エムポックス(Mpox)」**という新しい名称が広く使われるようになっています。
この呼び名の変更は、2022年に世界保健機関(WHO)が提唱したものです。
病名に動物名や地名を含めることによる差別や偏見を防ぐために、より中立的で誤解のない名称として「エムポックス」が採用されました。
📝 病名から差別や誤解をなくす
例えば「エボラ」「中東呼吸器症候群」など、地名・動物名が使われた病名が原因で偏見や差別が起きたケースがありました。
その反省から、WHOは近年「中立的な名称」を推奨しています。
この方針は国際的にも徐々に浸透しており、日本でも厚生労働省や自治体が発信する資料において、
「エムポックス」という表記が標準化されつつあります。
◆ エムポックスは、どんな病気?
エムポックスは、「エムポックスウイルス(Orthopoxvirus属)」によるウイルス性感染症です。
もともとはアフリカ中西部で自然宿主(野生動物)を介して流行していた病気でしたが、
2022年以降、世界的に感染が拡大し、アジア・欧米を含む各地で感染報告が相次ぎました。
主な感染経路は…
- 動物から人へ:感染した動物との接触
- 人から人へ:発疹や体液、飛沫などを通じた濃厚接触
📌 感染力は新型コロナほど強くありませんが、皮膚や粘膜の接触を通じて広がりやすく、発疹や発熱などの症状が数週間続くこともあります。
症状が強い場合は入院を要するケースもあるため、軽視はできません。
◆ 世界的な広がりと、日本での現状
2022年、感染拡大のスピードを受けて、WHOは**「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言しました。
アメリカやヨーロッパ諸国を中心に患者数が増加し、その後、日本国内でも複数の感染例が確認**されるようになります。
当初は「海外渡航歴のある人」からの感染がほとんどでしたが、現在では国内での市中感染も報告されており、
誰にとっても無関係とは言えない感染症になってきています。
特に最近の流行では、性的接触を通じた感染報告が多く、一部のコミュニティに対して重点的な注意喚起も行われています。
◆ 今、正しい情報が必要な理由
SNSやインターネットの情報の中には、不正確で誤解を招く内容も少なくありません。
「怖い病気」「人からすぐうつる」など、過度な不安を煽る一方で、実際の予防方法や感染リスクについて正しく理解できていないケースも目立ちます。
だからこそ、今必要なのは——
「正しい知識」で、必要以上に恐れず、冷静に備えること。
🧾 エムポックスの症状と潜伏期
〜発症のサインと感染のタイミングを正しく知ろう〜
なぜ「症状の流れ」を知っておくべきなのか?
エムポックスに感染した場合、どのような症状が出て、いつごろ発症するのかを知っておくことはとても大切です。
その理由は大きく3つあります:
- 🕒 早期発見につながる
- 🤝 他の人への感染拡大を防ぐ
- 🩺 重症化リスクのある人の早期対応が可能になる
このセクションでは、症状の進行段階・潜伏期間・重症化のリスクについて、やさしく丁寧に解説します。
🩺 エムポックスの症状は段階的に進みます
エムポックスの症状は、感染から数日〜3週間の潜伏期間を経て現れます。
その後、インフルエンザのような初期症状 → 皮膚の発疹へと進行していくのが典型的な経過です。
【STEP1】初期症状(1〜5日目)
感染後、まず現れやすいのが以下のような「全身症状」です:
- 🌡️ 高熱(38度以上)
- 🤕 頭痛
- 😣 倦怠感(だるさ)
- 💪 筋肉痛
- 🔴 リンパ節の腫れ(首・わきの下・足の付け根など)
🔍 特に注目すべきなのが「リンパ節の腫れ」。
エムポックスではこの症状がよく見られ、インフルエンザや新型コロナとの重要な違いとなっています。
【STEP2】発疹・皮膚症状(2〜4日目以降)
初期症状から数日後、皮膚に発疹が出始めます。これはエムポックスの最も特徴的な症状です。
▶ 発疹の特徴:
- 顔・手足・体幹などに出やすい
- **小さなぶつぶつ(丘疹)**として始まり
→ 水ぶくれ(水疱)
→ うみを持つ膿疱
→ かさぶたへと変化していきます - 発疹は痛みやかゆみを伴うことも
この発疹の経過は数日〜2〜3週間ほど続くことが多く、自然にかさぶたとなって剥がれ落ちるまで感染のリスクが続きます。
⏳ 潜伏期間と感染のタイミング
▶ 潜伏期間はどのくらい?
- 通常:6〜13日間
- 最短:5日間
- 最長:21日間
感染してすぐに症状が出るわけではなく、時間をおいてから発症します。
そのため、「あのときの接触が関係していたかも?」といった振り返りが重要になることもあります。
▶ 感染力が高まるタイミングは?
- 発症前の無症状の段階で感染するリスクは低いと考えられています
- 発疹が出始めてからが、もっとも感染させやすい時期
つまり、発疹の有無が感染リスクを判断する上で非常に重要です。
🚨 重症化するリスクがあるのはどんな人?
多くの感染者は軽症で済むケースが多いですが、以下の方は重症化のリスクが高いため注意が必要です:
- 🧬 免疫力が低下している方(HIV陽性者・がん治療中など)
- 🤰 妊娠中の方
- 🧒 小さなお子さん(小児)
- 👴 高齢者
こうした方が感染した場合は、入院治療が必要になる可能性もあるため、早めの受診・検査が大切です。
🧪 医師による診断と検査の流れ
「エムポックスかもしれない」と感じた場合は、自己判断せず、医療機関に相談しましょう。
医師は以下のポイントをもとに診断を行います。
✅ 診察で確認する内容:
- 発熱・リンパ節腫れ・発疹の有無
- 発疹の出た場所・変化の様子
- 海外渡航歴や感染者との接触歴
✅ 主な検査:
- 発疹部位のPCR検査(綿棒などで拭き取り)
- 必要に応じて血液検査や問診
🏥 日本では、保健所と連携した「確定診断」が必要です。
必ず医師の指示に従い、受診前には事前連絡を入れてください。
✅ まとめ:症状を見逃さないことが予防の第一歩
- エムポックスは発熱とリンパ節の腫れ → 発疹へと進行します
- 潜伏期間が長いため、感染のきっかけを見逃しやすい
- 発疹が出たら感染リスクが高まるため、他者との接触に注意
- 重症化しやすい人は、症状が軽くても早めに受診を
🧭 感染経路とリスクが高い場面
~どんな時にエムポックスは感染しやすいのか~
◆ 感染対策の第一歩は、「感染経路を正しく知ること」
エムポックスの予防を考えるうえで、まず必要なのは「どんな経路で感染するのか」を理解することです。
とくに2022年以降の世界的流行では、従来は稀とされていた人から人への感染が数多く確認されています。
つまり、私たちの日常生活の中でも、感染リスクがゼロではないということです。
🔄 基本的な感染経路
エムポックスの感染は、主に次の3つのルートで広がるとされています。
① 皮膚や粘膜の「直接接触」
- 感染者の発疹・膿疱・かさぶたに触れることでウイルスが体内に侵入
- 特に発疹が出ている皮膚・粘膜との接触はリスクが高い
- タオル・寝具・衣類などを通じた「間接接触」でも感染する可能性あり
② 飛沫による感染
- くしゃみ・咳・会話時の飛沫が、口や鼻、目の粘膜に入ることで感染
- 特に長時間・至近距離での接触がリスクを高める
💬 日常のすれ違いや短時間の会話で感染するリスクは低いですが、
マスクなしの密接な対話などは注意が必要です。
③ 性的接触を通じた感染
- 2022年以降、性的関係に伴う感染報告が急増
- 性交時の皮膚接触や、性器まわりの発疹・体液による感染が主な要因
- オーラルセックスや接吻など、密な接触でも感染する可能性あり
※**空気感染(空中に漂うウイルスの吸引)**は、現在のところ確認されておらず、
新型コロナウイルスほどの感染力はないとされています。
⚠ なぜ「性的接触」が注目されているのか?
エムポックスは、医学的には「性感染症(STI)」ではありません。
しかし、感染の多くが濃厚な皮膚接触を伴う性行為の場面で起きているため、性感染症に近い形での注意が必要とされています。
とくに世界的には、
MSM(Men who have Sex with Men)=男性間の性的接触による感染例が多く報告されており、
WHOや各国の公衆衛生機関もこの点に言及しています。
🧩 これは特定の人々を「非難する」意図ではなく、
感染パターンを理解するための疫学的な情報です。
☑ 大切なこと
- 感染のリスクは性別や性的指向に関係なく、誰にでもある
- 重要なのは、「密接な接触の場面があったか」という点です
🏠 日常生活・家庭・職場での感染リスク
エムポックスは、医療現場や家庭内でも感染が起こり得る感染症です。
以下のような状況では、特に注意が必要です:
🚩 感染リスクが高くなる場面
- 家族内での密な接触(寝具・タオルの共有など)
- 看護・介護などで発疹に触れる場面がある
- 発疹や膿疱に触れた手で顔をこする・目を触る
👩⚕️ 医療・介護現場での注意点
医療従事者や介護職の方は、次のような対策が推奨されます:
- マスク、手袋、ガウンなどの**PPE(個人防護具)**を適切に着用
- 発疹がある患者さんのケア時には手指消毒の徹底
- 使用後のリネン・器具などの適切な廃棄・消毒
🤲「接触しただけでうつる」は本当?
日常生活での軽い接触(例:握手、同じ空間での会話)だけで、
すぐに感染するわけではありません。
ただし、以下のような条件が複数重なる場合は注意が必要です:
- 感染者に発疹や膿疱がある
- 肌と肌の直接接触があった
- 感染者の寝具・衣類を共用した
- 15分以上の近距離での会話・身体的接触があった
こうした「濃厚接触」が確認された場合は、
保健所などの指示に従って健康観察や検査を受けることが推奨されます。
✅ まとめ:誰にでも起こり得る感染だからこそ、冷静に対応を
- エムポックスの感染は直接接触・飛沫・性的接触などで起こります
- 密な接触があった場面を振り返り、**「リスクがあったかどうか」**を判断しましょう
- 「特定の人だけが感染する病気」ではありません
- 感染者が出た場合も、正しい知識と冷静な対応が周囲の安心につながります
日本での感染状況と報告事例
最新の厚生労働省等の公表データをもとに、日本国内でのエムポックスの発生状況を整理します。流行の傾向や重要な報告が含まれます。
国内発生数の推移と現状
- 日本では、2022年7月に初めてエムポックス患者が確認されました。
- 2023年以降、散発例が続いており、2025年9月12日時点で 254例 の患者が報告されています。
- 発症日が判明している例をもとにした流行曲線も示されており、直近の週でも引き続き発症例が認められています。
クレード(系統)の特徴と新たな報告事例
- エムポックスウイルスには主に クレードⅡ(ⅡaおよびⅡb)、および 中央アフリカ型クレードⅠ(ⅠaおよびⅠb) があります。
日本で多数報告されてきたのはクレードⅡ系統です。 - 2025年9月、クレードⅠb の感染が日本で初めて確認されました。20代女性で、アフリカへの渡航歴があります。
感染者の特徴と感染経路
- 多くの例で 海外渡航歴のない患者 が報告されており、国内での感染が一定レベルで続いていることを示しています。
- 日本国内では、男性が多数を占めることが多いという報告がありますが、女性の例も含まれています。特に前述のクレードⅠb例は女性。
- 感染経路として予想・確認されているものは、「発疹部位の皮膚病変との接触」「性的接触」「寝具・衣類などの間接接触」など。
重症度・対策状況
- クレードⅠ系統は一般にクレードⅡよりも重症化リスクが高いとされており、日本でもクレードⅠb感染例が確認されたことで、警戒が高まっています。
- 感染症法上、日本では4類感染症に指定されており、医師の届出義務もあります。これにより、疑い例の把握と報告が制度的に整備されています。
- 厚生労働省は、自治体・医療機関と協力し、サーベイランス(監視体制)の強化、発症例・疑い例の報告促進、情報公開を行っています。
📊 日本での感染状況と報告事例
〜最新データで見るエムポックスの国内動向〜
◆ かつてはアフリカの風土病、いまや日本でも報告が
エムポックスは元々、アフリカ地域を中心に限定的に発生していたウイルス性感染症でした。
しかし2022年以降、世界的な広がりを見せる中で、日本国内でも継続的な感染報告が行われています。
このセクションでは、国内の発生状況、地域別の分布、診断週ごとの推移、ウイルスの系統(クレード)情報など、最新の統計とともに解説します。
🗾 都道府県別の感染者数と分布傾向(2025年3月時点)
日本国内で最初に感染者が確認されたのは、2022年7月25日・東京都でした。
その後、海外渡航歴のない感染者も現れ始め、市中感染の可能性が示唆されるようになっています。
🔢 累計感染者数(2025年3月21日時点/厚生労働省報告)
| 都道府県 | 累計症例数 |
| 東京都 | 約188例 |
| 大阪府 | 約22例 |
| 神奈川県 | 約7例 |
| 千葉県 | 約6例 |
| 埼玉県 | 約5例 |
| 愛知県 | 約5例 |
🏙️ 東京都だけで全国の約75%以上を占める
感染者は都市部に集中しており、とくに東京都での報告が顕著です。
この背景には、人口密度の高さ、接触機会の多さ、検査・診断体制の整備などが影響していると考えられます。
📈 診断週別の症例推移:ピークと現在の傾向
エムポックスの国内感染は、単発ではなく時系列的な波を伴って推移しています。
🕒 主な傾向(2022年第18週〜2025年第10週)
- 2022年7月:国内初症例を確認
- 以降、週1〜5件の報告が続く
- 2023年5〜8月:報告数が増加し、週10例近くのピークも発生
- 2024年以降は落ち着きを見せ、週1〜3件の散発的な報告へ
- 2025年現在:週0〜2件で推移。安定傾向ながら収束には至らず
📌 「爆発的流行」は起きていないが、感染が持続的に続いている状況が明らかです。
🧬 クレード(系統)の違いと新たな報告例
エムポックスウイルスには、いくつかの**遺伝的系統(クレード)**が存在します。
国内で多く報告されていたのは、比較的症状が軽いとされる「クレードⅡb」です。
しかし、2025年9月には以下のような新しい事例が確認されました:
⚠ 日本初の「クレードⅠb」感染報告(2025年9月)
| 項目 | 内容 |
| 感染者 | 20代女性 |
| 渡航歴 | アフリカ中部への渡航あり |
| 系統 | クレードⅠb(重症化リスクやや高め) |
| 備考 | 国内での初確認例、現在は当局が監視体制を強化中 |
🧠 クレードⅠbは、重症化の報告が多いアフリカ中部の流行株。
今後、同系統の流入や市中感染の兆候がないか、注意深い観察が求められています。
👥 感染者の特徴と感染経路の傾向
国内で報告された感染者には、以下のような特徴が見られます。
📌 感染者の傾向(2022〜2025)
- 性別:男性が多数(特に20〜40代)だが、女性の報告も一部あり
- 感染経路:皮膚接触・性的接触が中心。公共交通機関などでの感染は極めて稀
- 渡航歴:当初は渡航者中心だったが、現在は国内感染(市中感染)例も増加
🧩 市中感染が確認されている以上、「海外に行っていないから大丈夫」とは言えない状況になっています。
🛡️ 日本国内の公的対策と個人でできる対応
エムポックスは日本では**感染症法に基づく「4類感染症」**に分類されており、以下のような公的対応が行われています。
🏥 公的な対応体制
- 診断後の届出が義務化(医療機関 → 保健所へ)
- 感染者の行動履歴の調査・濃厚接触者の健康観察
- 一部対象者へのワクチン接種検討中(天然痘ワクチンベース)
👤 個人でできる対策
- 発熱や発疹がある場合は早めの受診・事前相談を
- 感染が疑われる場合、他者との接触を控える
- 公的情報(厚労省・自治体)をチェックし、誤情報に惑わされない
✅ まとめ:現状は“収束”ではなく“継続的な注意”が必要
- 東京都を中心に感染例は継続中、新しいクレードも流入
- 報告数は減少傾向だが、感染の完全終息とは言えない
- 性別や渡航歴に関係なく、誰もがリスクを持つ感染症
- 日々の行動や情報収集が、自分と周囲を守る第一歩
📚 出典・参考資料
- 厚生労働省 エムポックス関連報告(2025年3月・9月)
- 国立感染症研究所 感染動向データベース
- 各自治体の感染症週報
🛡️ 予防方法とワクチン情報
~日常の工夫と正しい知識が、感染予防のカギ~
◆ 日常生活の中で、感染リスクは“ゼロ”にできない
エムポックスは主に接触によって感染するウイルス性感染症です。
そのため、身近な暮らしの中に感染リスクが潜んでいることを意識し、自分と家族を守る行動が求められます。
このセクションでは、すぐに実践できる予防策と、国内でのワクチン対応についてわかりやすくまとめています。
🧴 日常生活でできる予防対策
感染経路をふまえ、3つの基本的な予防ポイントを心がけましょう。
① 接触を避ける(接触感染対策)
- 感染者の発疹・かさぶた・膿疱には絶対に触れない
- 感染者が使用した衣類・タオル・寝具は洗濯や消毒を徹底
- ハンドタオル・下着・枕カバーなどは共用を避けて、個別に管理
② 飛沫・粘膜への感染を防ぐ
- 感染が疑われる人との近距離での会話や飲食を控える
- 密閉空間ではマスク着用が有効
- 咳やくしゃみの際はティッシュや肘で口を覆う(咳エチケット)
③ 衛生管理をこまめに
- 手洗い(石けん+流水で20秒以上)やアルコール消毒を習慣に
- 発疹や排泄物などに触れた場合は、必ず手洗いを徹底
- 家庭内に感染者がいる場合は、使い捨てマスク・手袋の活用が有効
⚠ 特に注意したい3つの場面
以下のようなシチュエーションでは、感染リスクが高まる可能性があります:
1. 性的接触や密着した関係
- 発疹がある部位への接触により感染する可能性が高い
- コンドームだけでは完全に予防できないため、相手の健康状態にも注意を
2. 医療・介護現場での対応
- 感染者に接する業務では、PPE(マスク・手袋・ガウン等)を正しく装着
- 患者のリネンや器具の適切な処理・消毒も重要
3. 外泊や旅行時の感染リスク
- 宿泊施設では、共用のタオル・枕・シーツ類の衛生状態に注意
- 不特定多数が使う場所では、接触を最小限に抑える工夫が有効
💉 ワクチン情報:現在の日本の対応状況
日本では、エムポックス対策として天然痘ワクチンを応用したワクチンが用意されています。
💊 使用されているワクチン
- 乾燥細胞培養痘そうワクチン(LC16m8)
→ 本来は天然痘用に開発されたワクチンですが、エムポックスにも約85%の予防効果があると報告されています(WHO)。
👥 接種対象者(2025年現在)
- 感染者との濃厚接触があった方(看護・性接触など)
- 感染リスクの高い集団(例:MSM、HIV陽性者など)
- 医療従事者・検査技師など、感染者対応に関わる職種
❗ 一般の方への広範な接種は実施されていません。
今後の感染状況次第で、接種対象が拡大される可能性があります。
💠 ワクチン接種による効果と副反応
- 接種1回で発症予防効果は約85%(WHO)
- 副反応としては、注射部位の腫れ・発熱・筋肉痛などが一時的に起こることがあります
- 免疫不全状態・妊娠中の方は、必ず医師と相談のうえ接種を検討
🏥 ワクチン接種体制と今後の課題
現在、日本では感染症法に基づく「臨時接種」体制の整備が進められています。
現状の取り組み
- 自治体単位でのワクチン配備・接種体制の構築
- 感染拡大地域や対象集団への優先接種の検討
- ワクチン供給量の確保・安定供給の調整
今後の課題
- 正確な情報の発信と、誤解・偏見への対策
- ワクチンの安全性と必要性を、わかりやすく伝える啓発活動
- 希望者が安心して接種を選択できる環境づくり
✅ まとめ:予防の基本は「正しい行動と正確な知識」
- エムポックスは接触・飛沫によって感染する
- 日常生活の中でも、シンプルな予防行動でリスクは下げられる
- ワクチンは高リスク層向けに限定的に提供中。今後に備えた整備が続いている
- 大切なのは、「怖がる」のではなく、「知って備える」という姿勢です
📘 参考情報
- 厚生労働省「エムポックスに関するQ&A」
- 国立感染症研究所「エムポックス関連資料」
- WHO「Mpox vaccination guidance」(英語)
🐒 サル痘とエムポックスの違い
~名前が変わっただけ?何が同じで、何が違うのか~
◆ 結論:エムポックスとサル痘は“同じ病気”です
「エムポックス(Mpox)」と聞くと、「サル痘とは違う病気なの?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、両者はまったく同じウイルス感染症を指しています。
病原体は**エムポックスウイルス(旧・サル痘ウイルス)**で、感染経路や症状、治療法に医学的な違いはありません。
🗂️ なぜ名前が変わったのか?
名称の変更は、医学的な理由というよりも、社会的・人道的な配慮に基づいています。
📌 背景と目的:偏見をなくすための名称変更
- 「monkey(サル)」という言葉が、特定の地域(アフリカ)や集団に対する偏見・差別を助長する恐れがあるとされていた
- 感染症の名前に動物名や地名を含めることは、過去にも差別的な印象を与えてきた(例:スペイン風邪、中東呼吸器症候群など)
- こうした課題を踏まえ、WHOは2022年11月に「エムポックス(Mpox)」という新名称を正式採用
1年間の移行期間を経て、「monkeypox」という表記は廃止され、
現在は日本でも厚生労働省や日本感染症学会が「エムポックス」の使用を推奨しています。
🧪 医学的には変わっていない:違いは“名称だけ”
「名前が変わったのなら、病気の内容も変わったのでは?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、ウイルスそのもの、症状、治療法などには一切の変更はありません。
以下の表をご覧ください:
| 項目 | エムポックス(Mpox) | サル痘(Monkeypox) |
| 🦠 病原体 | 同じ(エムポックスウイルス) | 同じ |
| 🧬 感染経路 | 同じ(接触・飛沫) | 同じ |
| ⏳ 潜伏期間 | 約6〜13日(最長21日) | 同じ |
| 🤒 臨床症状 | 発熱、リンパ節の腫れ、発疹など | 同じ |
| 💉 ワクチン対応 | 天然痘ワクチン(LC16m8等) | 同じ |
✅ 「病気の名前だけが変わった」
それ以外の医学的定義・感染対策には変更はありません。
🌍 名称変更がもたらす“メリット”と“課題”
✅ メリット
- 差別や不安を和らげる名称への転換
- 医療現場・報道機関・教育機関での中立的な表現が可能に
- 世界中での感染症対策における表記の統一と一貫性
⚠ 課題
- 一般の方の認識がまだ**「サル痘」のままで検索するケースが多い**
- 医学論文や過去の資料は今でも「monkeypox」表記が主流のため、情報検索がやや複雑に
- メディアや公的機関では、「エムポックス(旧サル痘)」と併記するケースが多い
名前は変わっても、中身は変わらない
- 「エムポックス」と「サル痘」は同じウイルスによる同じ感染症
- 名前の変更は、差別・偏見の防止を目的とした社会的な配慮
- 医学的な内容(症状・治療・ワクチン対応など)には変更は一切なし
- 当面は「エムポックス(旧サル痘)」と併記する表現が現実的
📌 今後は、「エムポックス」という名称が標準的になると予想されますが、
過去の情報や記事は「サル痘」と表記されていることも多いため、両方の名称を知っておくと情報収集に役立ちます。
🩺「もしかしてエムポックスかも…」と思ったときの行動ガイド
~落ち着いて、正しい一歩を踏み出すために~
エムポックスが気になる症状が出たとき、あるいは感染の可能性がある場面にいたとき——
「どうすればいいの?」「病院に行くべき?」「家族にうつさない?」
そんな不安を感じたら、まずは正しい知識と冷静な判断が大切です。
このセクションでは、感染が疑われるときの確認ポイントや、受診までの流れ、自宅療養時の注意点まで、具体的にわかりやすく解説します。
✅ まず確認したい「症状」と「状況」
以下に心当たりがある方は、感染の可能性を考えて一歩踏み出しましょう。
◆ 主な症状チェック
- 38℃以上の発熱
- 強い倦怠感、頭痛、筋肉痛
- 首・わき・足の付け根のリンパ節の腫れ
- 顔・手足・体幹にかけての発疹や膿疱
特に、リンパ節が腫れて痛む症状は、エムポックスの重要な特徴です。
◆ 感染リスクが高まる場面
- 感染者との直接的な身体接触があった
- 性的接触を含む密接なふれあいがあった
- 感染拡大中の地域・施設に出入りしていた
- 3週間以内に海外に渡航(特にアフリカ・中南米など)
📞 病院に行く前に、必ず「電話で相談」!
感染の疑いがあるときは、直接来院する前に、まずは連絡を。
不要な接触を避け、他の患者さんや医療スタッフを守るためにも重要なステップです。
◆ 相談先の一例
- 最寄りの 保健所
- かかりつけの クリニックや病院
- 都道府県の 感染症相談窓口
- 厚生労働省HPに掲載の エムポックス対応医療機関リスト
📌【ポイント】
「症状がある」「接触歴がある」など、気になる点は正直に伝えましょう。
状況に応じて、受診のタイミングや検査機関を案内してもらえます。
🏥 医療機関での対応フロー
医師の判断に基づき、次のような対応が行われます。
◆ 主な対応内容
- 発疹部のPCR検査(綿棒で患部を拭い、遺伝子検出)
- 問診・視診(発熱の経過、発疹の場所、リンパ節の腫れなど)
- 感染リスク評価(年齢・持病・妊娠の有無など)
確定診断が出た場合、保健所と連携した療養指示が行われます。
エムポックスは感染症法上「4類感染症」に指定されているため、指示に従って行動することが必要です。
🏡 自宅療養になる場合の注意点
症状が軽く、入院を必要としないと判断された場合、自宅での療養となることがあります。
◆ 家庭内での感染防止ポイント
- 発疹やかさぶたはガーゼなどで覆い、露出を避ける
- タオル・寝具・衣類は個別管理(共有しない)
- マスクを着用し、会話時の飛沫をブロック
- トイレ・洗面所の消毒をこまめに
- 家族との接触は最小限に、可能であれば別室で過ごす
特に、小さなお子様や高齢者がいる家庭では、しっかりと対策を行いましょう。
◆ 同居家族がいる場合
- 感染者と部屋・食事を別に
- 家族は3週間の健康観察対象
- もし家族に症状が出たら、すぐに医療機関へ相談を
⏱ 回復の目安と復帰のタイミング
エムポックスは、多くの場合は自然に治るウイルス感染症です。
ただし、周囲への感染を防ぐために、明確な回復基準を守る必要があります。
◆ 療養終了の目安
- 発疹がすべてかさぶたとなり、自然に剥がれ落ちた
- 発熱・全身症状がなくなった
- 医師または保健所から「療養終了」の指示がある
📌 学校や職場への復帰は、「もう大丈夫かな?」と自己判断せず、専門機関の指示に従いましょう。
📣 心配しすぎず、でも放置せず
~信頼できる情報と専門家の力を頼ってください~
エムポックスについては、SNSなどで根拠のない情報が広がることもあり、
必要以上に不安になってしまうケースもあります。
だからこそ、以下のような公的な情報源を参考にすることが大切です。
◆ 信頼できる情報源
- 厚生労働省 エムポックス情報ページ
- 国立感染症研究所(NIID)
- 地方自治体の保健所や公式サイト
- かかりつけ医・感染症専門医の判断
🧘♀️ まとめ:大切なのは「正しく恐れて、冷静に動くこと」
エムポックスは、適切に対応すれば十分に予防・管理可能な感染症です。
症状があっても、過度に恐れることはありません。大事なのは…
- 落ち着いて体調を観察する
- 専門家や公的機関に相談する
- 周囲への感染を防ぐ行動をとる
自分の健康を守るだけでなく、家族や社会の安心にもつながる行動を、あなた自身の一歩から始めましょう。
🧭 まとめ:正しい知識で、落ち着いて向き合うために
エムポックス(旧サル痘)は、まだ日本では広く知られていない感染症かもしれません。
ですが、都市部を中心に感染が続いており、誰もが“知っておくべき”身近なウイルスになりつつあります。
過剰に恐れる必要はありません。
しかし、正確な知識をもとに、冷静に備えることが、あなた自身と大切な人を守る第一歩です。
🔍 本記事のポイント振り返り
| テーマ | 要点まとめ |
| エムポックスとは? | WHOが2022年に名称変更。差別や偏見を避けるために「サル痘」から改称。病気の本質は同じ。 |
| 主な症状・潜伏期間 | 発熱・リンパ節の腫れ・発疹が特徴。潜伏期間は5〜21日。 |
| 感染経路 | 皮膚接触・飛沫・性的接触など。長時間の近距離接触や寝具の共有などにも注意。 |
| 日本の感染状況 | 累計254例(2025年3月時点)。東京都に集中。市中感染も報告あり。 |
| 予防策とワクチン | 手洗いや接触回避が基本。LC16m8ワクチンが特定対象者に使用中。 |
| 感染が疑われる場合の対応 | 直接受診せず、まずは保健所や医療機関に電話相談を。自宅療養でも感染対策を徹底。 |
🧠 「正しく恐れる」ために大切なこと
SNSや噂話によって、「誰が感染するのか」「どんな病気なのか」という誤解が広がることがあります。
特に、「特定の人だけが感染する病気」という誤った印象は、感染対策の妨げにもなりかねません。
エムポックスは、誰にでも感染のリスクがある一般的なウイルス感染症です。
私たち一人ひとりが、正しい情報と向き合う姿勢を持つことが、地域全体の安心につながります。
📚 信頼できる情報源を活用しましょう
- 厚生労働省公式サイト
- 国立感染症研究所(NIID)
- FORTH(海外感染症情報)
- 各自治体の保健所
不安を感じたときこそ、こうした専門機関の発信する情報をもとに、冷静な判断を心がけてください。
💬 最後に
感染症との向き合い方は、「怖がる」ことではなく、「備える」こと。
そして、「差別する」ことではなく、「支え合う」ことです。
本記事が、皆さん一人ひとりの冷静な行動や、周囲への思いやりにつながれば幸いです。