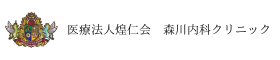③夜間頻尿が激減!生活習慣病も整う『睡眠改善3時間ルール』とは?
『就寝前3時間ルール』とは?
「睡眠の質を上げたい」――そう考える人にとって、まず見直すべきは“就寝前の過ごし方”です。
なかでも重要なのが、「夕食」「入浴」「スマホ」のタイミング。これらをそれぞれ就寝の3・2・1時間前までに済ませるというのが、『就寝前3時間ルール』です。
このシンプルなルールを守ることで、体内時計やホルモン分泌、自律神経の働きがスムーズになり、睡眠の質が飛躍的に向上します。以下、それぞれのポイントを詳しく解説します。
🕒 就寝3時間前の夕食:血糖値の安定と胃腸の休息を促す鍵
睡眠の質を左右する生活習慣の中で、最初に見直したいのが夕食の時間帯です。
特に中高年になると、若い頃と比べて胃腸の働きが緩やかになるため、就寝直前の食事は“眠りの質”を著しく低下させる要因となります。
就寝直前の食事がもたらすリスクには、次のようなものがあります:
- 胃が活発に働いたまま眠ることで、深い眠り(ノンレム睡眠)に入りにくくなる
- 食後の血糖値急上昇 → インスリンの過剰分泌 → 血糖コントロールの乱れ
- 胃もたれや逆流性食道炎のリスクが高まる
これらを防ぐためには、就寝の3時間前までに食事を終えるのが理想です。
たとえば23時に寝る場合は、遅くとも20時までに夕食を済ませておくようにしましょう。
このタイミングであれば、血糖値が自然に安定し、胃の消化も一段落した状態で眠りにつくことができます。
加えて、夕食の「内容」も重要です。脂っこい料理や塩分の多い食品は消化に時間がかかるだけでなく、体内の水分バランスを乱し、夜間のトイレ回数を増やす一因にもなります。
高たんぱく・低脂肪・低塩分のメニューを意識すると、より深い眠りにつながります。
🛁 就寝2時間前の入浴:深部体温を“ゆっくり下げる”のがカギ
次に重要なのが、「入浴のタイミング」です。
人は、深部体温(体の奥の温度)がゆるやかに下がるときに自然な眠気を感じるようにできています。
この体温のリズムを上手に活かすには、ぬるめのお湯(38〜40℃)で15〜20分ほど入浴し、就寝の2時間前までにお風呂を終えるのが理想的。
例えば23時に寝るなら、21時までに入浴を済ませるのが目安です。
この“入浴→体温上昇→ゆるやかに体温低下”というプロセスにより、入眠に適した体内環境が自然と整っていきます。
入浴のメリットはそれだけではありません。
- 血流の促進 → 筋肉の緊張が緩む
- 副交感神経が優位になり、リラックスモードへ移行
- 血圧・心拍数の安定 → より深い眠りをサポート
ただし、入浴直後はまだ体温が高く、交感神経が優位な状態にあるため、入浴後すぐに寝床に入るのは逆効果です。
最低でも1.5~2時間の“体温クールダウン”の時間を設けることで、より自然な眠りへと導かれます。
📵 就寝1時間前のスマホOFF:ブルーライトと脳の覚醒を避ける
最後に、現代人が最も見落としがちなポイント――それが就寝前のスマートフォン使用です。
スマホやタブレット、PCから発せられるブルーライトは、脳に“今は昼だ”と錯覚させる刺激となり、メラトニン(眠気を誘うホルモン)の分泌を抑制します。
さらに、SNSやニュース、動画の視聴などによって交感神経が活性化し、脳が覚醒モードに突入。
こうなると、スムーズな入眠は難しくなります。
特に中高年は、加齢とともにメラトニンの分泌量が低下するため、ブルーライトの影響をより強く受けやすい傾向があります。
そのため、就寝の1時間前にはスマホやPCから離れ、アナログな過ごし方へシフトすることが推奨されます。
たとえば、
- 静かな音楽を聴く
- 紙の本を読む
- ストレッチや深呼吸などのリラックス習慣を取り入れる
など、“デジタルデトックス”の時間を持つことで、睡眠の質は大きく変わります。
✅ まとめ:3・2・1時間前の準備が、深い眠りをつくる
行動 推奨タイミング 主な目的
夕食 就寝の3時間前 胃腸の休息・血糖値安定
入浴 就寝の2時間前 深部体温の調整・リラックス
スマホ使用 就寝の1時間前まで メラトニン分泌促進・脳の沈静化
「就寝前3時間ルール」は、習慣を少し整えるだけで得られるセルフケアの第一歩。
無理のない範囲から、ぜひ取り入れてみてください。