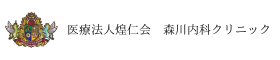④睡眠時無呼吸症候群
原因とメカニズム
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、単純に「太ったからいびきをかく」というだけの病気ではありません。
気道を塞ぐ構造的な要因や加齢、ホルモンバランスの変化など、複数のリスク因子が複雑に絡み合って発症します。
なかでも最も多いのは、上気道(のどや鼻の空気の通り道)が狭くなることで生じる「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」です。
ここでは、主な原因とメカニズム、さらに性別や年齢によるリスクの違いを見ていきましょう。
主な原因とそのメカニズム
■ 肥満(特に首まわりの脂肪)
体重が増えると、首の周囲に脂肪が蓄積し、気道を圧迫しやすくなります。
特にBMIが25以上の人、内臓脂肪型の肥満体型は要注意。睡眠中に気道が塞がれやすく、無呼吸を誘発します。
■ 顎の形(小さい・後退している)
下顎が小さい、もしくは後退している人は、舌や軟口蓋が喉に迫り、気道を狭めやすくなります。
日本人に比較的多い骨格的特徴で、「顔が小さい」「顎が細い」といった点がリスクにつながります。
■ 舌の大きさ・舌根の落ち込み
睡眠中に舌が喉の奥に落ち込み、気道を塞ぐケースです。
仰向け寝やアルコール摂取、強い疲労で筋肉が弛緩するとさらにリスクが高まります。
■ 鼻づまり・アレルギー性鼻炎
鼻呼吸が妨げられると口呼吸が増え、舌が下がりやすくなり、結果的に気道が閉塞されます。
慢性的な鼻炎やアレルギーを放置すると、SASのリスクも高まります。
■ 加齢による筋力低下
年齢とともに喉や舌の筋肉が弱まり、気道が狭まりやすくなります。
特に50代以降にSASの発症率が増えるのは、この「加齢による筋肉のゆるみ」が背景にあります。
性別・年齢による違い
■ 男性
SASは男性に多く、特に40〜60代の働き盛り世代で目立ちます。
肥満、飲酒、喫煙、ストレスなど複数の要因が絡みやすく、生活習慣の見直しが予防のカギとなります。
■ 女性
女性は閉経前後からリスクが上昇します。
女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)が減少し、筋肉の保護作用が弱まるためです。
加えて、女性の場合は「大きないびき」よりも抑うつ傾向や疲労感として症状が出やすく、見逃されやすい点が特徴です。
■ 子ども
小児のSASは、アデノイドや扁桃肥大、アレルギー性鼻炎などが主な原因です。
発達期に十分な睡眠が得られないと、集中力の低下や多動傾向、学業への影響につながることもあります。
子どものいびきや口呼吸が目立つ場合は、早めに耳鼻科や小児科での相談が望まれます。
まとめ:多因子性で進行する病気
SASは、ひとつの要因だけでなく 体型・骨格・年齢・性別・生活習慣 といった様々な要素が組み合わさって発症します。
自分の生活や身体的特徴を振り返り、当てはまる点がある場合は、次に紹介する「検査と診断の流れ」を確認し、早めの受診を検討しましょう。