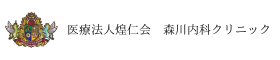⑤睡眠時無呼吸症候群
検査と診断の流れ
何科に行けばいい?受診前に知っておきたいこと
「いびきが気になる」「日中に強い眠気がある」──そんなときに最初に迷うのが、「何科を受診すればいいのか?」という点です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、呼吸、睡眠、耳鼻咽喉、生活習慣など幅広い要因と関係しているため、診療科の選び方が大切です。
診断の流れをあらかじめ知っておくことで、受診後のステップがぐっとスムーズになります。
どの診療科を受診すべきか
SASの診断には、以下の診療科が対応しています。
- 耳鼻咽喉科:鼻や喉の構造に異常がないかを確認
- 呼吸器内科:呼吸機能や無呼吸の頻度を評価
- 睡眠外来・睡眠センター:専門設備を備え、総合的な検査・診断が可能
- 内科(総合診療科):最初の相談窓口として活用できる
多くの場合、これらの科で問診や簡易検査を行い、必要に応じて専門的な検査へと進みます。
診断までのステップ
1. 問診と簡易評価
- 睡眠の状況、日中の眠気、いびきの有無などをヒアリング
- **エプワース眠気尺度(ESS)**といったチェックリストで眠気の程度を数値化
2. 簡易検査(自宅スクリーニング)
- 医師から貸与される小型機器を自宅で一晩装着
- 呼吸の流れ、血中酸素濃度、心拍、いびき音などを測定
- 結果に応じて、精密検査(PSG)へ移行
3. 精密検査:終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
かつては「入院して一泊検査」が基本でしたが、近年では自宅で実施できる方法も普及しています。
(1)病院で行う入院型PSG
- 脳波・眼球運動・筋電図・心電図・呼吸・酸素飽和度などを同時に記録
- 無呼吸のタイプ(閉塞性/中枢性)、睡眠の質や回数を正確に分析
- 1泊入院で実施/保険適用可能
(2)在宅で行うPSG(自宅型ポリグラフィー)
- 検査機器を持ち帰り、自宅で装着して睡眠を計測
- 普段の環境で検査できるため、自然なデータが得やすい
- ただし、装着方法を誤ると測定エラーになるため、事前の説明が重要
PSGの診断基準(AHI:無呼吸低呼吸指数)
- 軽症:5〜15回/時間
- 中等症:15〜30回/時間
- 重症:30回以上/時間
この数値と症状をあわせて、治療方針(CPAP療法、マウスピース、生活習慣の改善など)が決定されます。
受診前に準備しておくとよいこと
- 家族からの指摘(いびき・呼吸停止など)をメモ
- 起床・就寝時刻や日中の眠気を記録
- 健康診断の結果や既往歴、服薬内容を整理
これらを持参することで、医師の診察や検査がスムーズになります。
まとめ:診断の第一歩は「疑いを持つこと」
睡眠中の異変は自分では気づきにくいものです。
少しでも不安を感じたら、まずは適切な診療科を受診し、簡易検査や在宅PSGから始めましょう。
早めの診断こそが、重篤な合併症を防ぐ最大の武器になります。